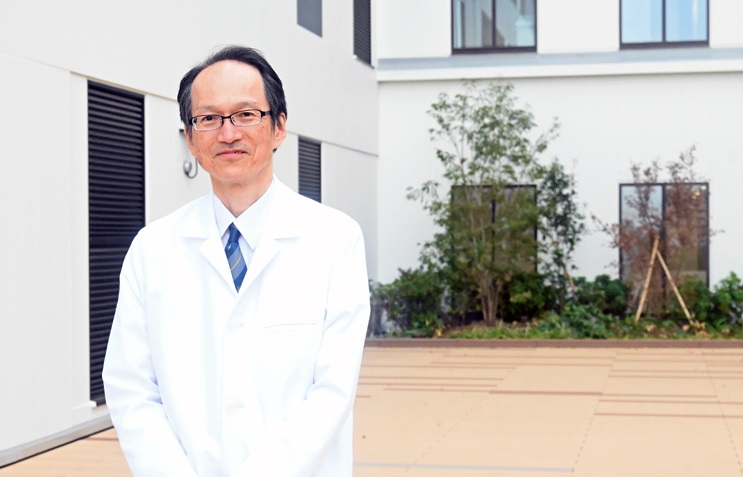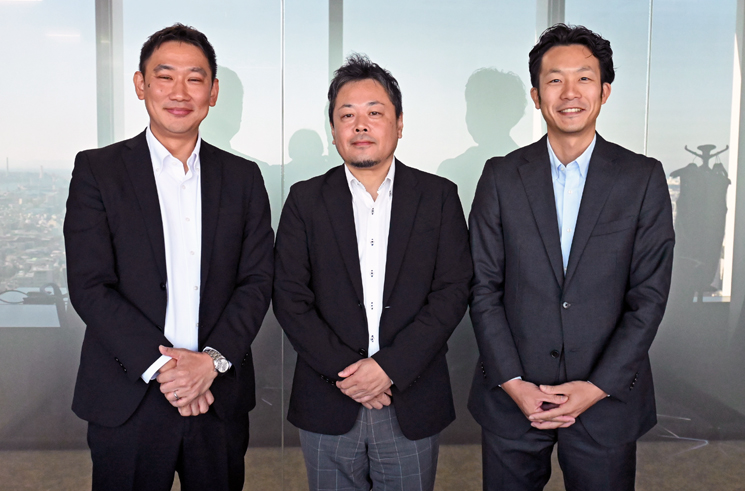ユビーが描く「医療機関業務にAIが根付く日常」――生成AIと問診AIが変える医療現場の新しいかたち
掲載日:

ユビーメディカルナビ
医療現場では、慢性的な人手不足のなかで、診療に加えて多くの文書作成や事務作業をこなさなければならない。医療の質を落とさず、同時に業務を効率化することは、現場にとって長年の課題だ。こうした状況に対し、AIを中核技術として医療支援に取り組むのが、医療スタートアップのユビー(東京・中央区)だ。
同社の医療機関向けAIサービス「ユビーメディカルナビ」は、生成AIと問診AIを組み合わせ、外来・病棟・事務業務までを横断的に支援する。事務作業を劇的に効率化する生成AIと、患者の声を精緻に拾い上げる問診AI。これらが組み合わさることで、医療現場の景色はどう変わるのか。医療現場での活用と今後の展望を追う。(医療テックニュース編集部 編集長 米谷知子)
創業の使命と技術基盤
ユビーは2017年に設立。医師の阿部吉倫氏と元エンジニアの久保恒太氏が共同代表を務める。両者は2013年から大学院での研究を基盤に、症状と疾患の関連性を解析するAIを開発してきた。そのAIは、約50名の外部医師の協力を得て5万本以上の医学論文を参照し、独自のアルゴリズムで構築したことが特長だ。
創業の背景には、代表の阿部氏が研修医時代に直面した「大腸がんの早期受診機会を逃した患者の死」がある。適切な時期に医療にアクセスできなかった経験を踏まえ、「適切な医療に早くつなげる」を、自社の社会的な使命として事業を展開する。同社は、「生活者」「医療機関」「製薬企業」の三分野に向けたサービスを提供し、医療機関と生活者をつなぐハブとして機能する。
医療現場の“相棒”で進化し続ける「ユビーメディカルナビ」
ここでは医療機関向けサービスに注目する。同社が開発した病院向けAIサービス「ユビーメディカルナビ」は、AIを中核技術に、医療機関の診療効率化と質の向上を支援するプラットホームだ。外来、病棟、事務部門など幅広い現場で、医療機関と生活者をつなぐ基盤として機能することを目指している。サービスは「ユビー生成AI」と「ユビーAI問診」の二本柱で構成する。
「ユビー生成AI」は、文書作成を中心に業務を効率化するサービス。具体的な成果では、退院時サマリーや看護サマリーなど診療報酬上で必須の文書作成時間を平均42.5%短縮し、心理的負担は27.2%軽減したという。さらに、インフォームドコンセント(十分な説明と同意)支援やカンファレンス議事録作成に加え、DPCコーディング支援機能など、用途を拡張している。
一方、「ユビーAI問診」は、患者が事前に入力した症状に基づいて動的に質問を追加し、医師が診療前に必要情報を把握できるようにするサービス。コロナ禍では、発熱外来で患者が車中から入力し、非接触で情報を収集できる仕組みとして機能した実績を持つ。現在、導入先は大学病院などの大規模施設に加え、100?500床規模の地域病院やクリニックにも広がっている。
現場が使いやすい技術設計とシステム連携の優位性
「ユビーメディカルナビ」の強みは、電子カルテに閉じない柔軟な連携性にある。多くの電子カルテベンダーでは、AI機能の参照データが電子カルテの標準的な範囲のデータに限定される場合が多いのに対し、同社のシステムは、部門システムを含め幅広く連携できる点が優位性になっている。
ユビーの生成AIは、電子カルテや部門システムのデータ連携に加え、音声入力にも対応する。例えば、医師が患者への説明を音声で記録すれば、システムが自動でテキスト化し、利用シーンに応じて文章・音声・画像を使い分けられる柔軟な仕組みを備えているため、医療現場の多様な業務に適応する。
生成AIの中核には、グーグルの生成AI「Gemini(ジェミニ)」を基盤モデルとしてメインで活用。システムは、3省2ガイドラインにも準拠し、法人向けの安全性を担保した基盤で運用されており、セキュリティーを確保している。
さらに、医師からのフィードバックを継続的に取り込み、医療機関ごとのプロンプト(指示文)の調整を行うことで、医療現場の多様な業務プロセスに適応できる。
β版で提供する「DPCコーディング支援」機能は、診療録(非構造化データ)とオーダー情報(構造化データ)を踏まえ最適なコーディングを行う必要があるため、非常に複雑で現場の業務負荷になりやすい状況に対して、AIがデータを自動で解析し、患者ごとに最適なコーディングを行えるように支援する。この仕組みは、医療現場の生産性向上だけでなく、病院経営の改善にも有用だ。
「AIが医療現場に定着する未来へ」ユビーの展望
同社は、「ほかの業界で当たり前に使われている生成AIを病院内で当たり前に使えるもの」とすることを目指し、規制やシステム面の課題解決に取り組んでいる。
今後は、生成AIの活用範囲を外来や病棟から地域医療連携へと広げ、医療情報の共有や遠隔診療への応用を進める方針だ。
海外展開も進めており、2022年の米国法人の設立以降、生活者向けと製薬企業向けの事業を展開。すでに30万人規模のユーザーを獲得した。今後は欧州を中心に先進国に進出し、最終的にはアジア・南米・アフリカなどにも展開する構想を掲げている。
これらの取り組みは、「すべての人が適切な医療に早くつながる社会をつくる」という創業理念とつながっている。