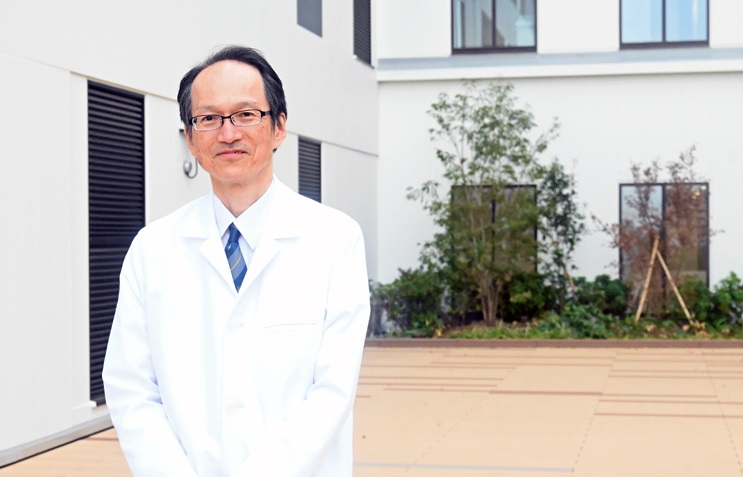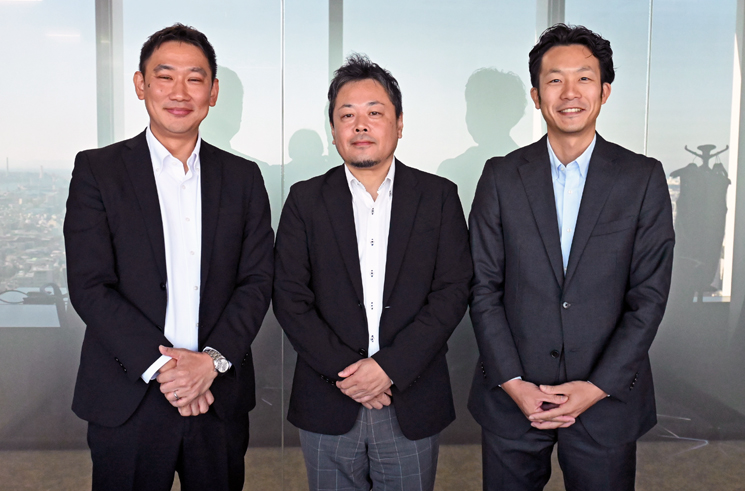滋賀県を変える「横のつながり」 病院医療情報システム担当者の集いが築く地域共助
掲載日:

「滋賀県病院医療情報システム担当者の集い」のメンバー(第5回参加者)
電子カルテをはじめとする医療情報システムの安定運用は、病院経営の根幹で、患者の安全に直結する。しかし、多くの医療機関、特に地域の中小病院では、情報セキュリティーやIT-BCP(事業継続計画)といった喫緊の課題に、少人数の担当者が孤軍奮闘する状況が続いている。
「滋賀県病院医療情報システム担当者の集い」は、こうした担当者の「横のつながり」を強化し、病院単独では解決できない課題を地域全体で乗り越えるためのプラットホームだ。なぜ、この集いは短期間で機能するようになったのか。また、担当者の間で「泣きつく先が見つかった」とまで言われるのか。その発足の経緯、他地域でも応用可能な運営の秘訣、そして第5回会議で繰り広げられた切実で熱量のある議論の全貌をレポートする。(医療テックニュース編集部 編集長 米谷知子)
孤立する担当者を救う「共助」のプラットホーム
多くの医療機関、とりわけ中小規模の病院では、医療情報システムを担う人材が限られ、担当者が孤立しがちだ。そして、情報セキュリティーやIT-BCP(事業継続計画)に、少人数で取り組まざるを得ない現状がある。
滋賀県で発足した「滋賀県病院医療情報システム担当者の集い」は、まさにこの課題に応える当事者主導のプラットホームである。2024年5月に発足し、年3回のペースで活動している。この集いは、単なる情報交換の場ではなく、地域医療のシステム基盤を共に支え合う「共助」の体制を築くことを明確な目標に掲げている。
事務局機能を大津赤十字病院の医療情報課が担い、現在は県内で20弱の病院が定期的に参加している。中心となって集いを推進する橋本智広・大津赤十字病院医療情報課課長は、「共助」を軸に、「自ら学ぶ」「相談する」姿勢を大切にしていると語る。これが、この集いの核心的な理念だ。
10年来の構想を動かした3人のキーパーソン
「滋賀県医療情報システム担当者の集い」の構想は、2013年に地域医療連携ネットワーク協議会「びわ湖あさがおネット」が設立された時点までさかのぼる。当時、理事を務めていた永田啓・滋賀医科大学名誉教授は、ネットワーク基盤の整備に加えて「医療情報に関する人材育成にも取り組むべきだ」と提案した。これが、いまの活動の源流となった。
ただ、この構想はすぐには形にならなかった。サイバーセキュリティーやIT-BCPの重要性が急速に高まり、国のガイドライン対応が複雑化するにつれ、少人数の担当者が幅広い業務を抱え込む状況が顕在化した。「自院だけでは判断できない」「相談できる相手がいない」といった声が病院の間で強まり、この“積年の課題”を実際の取り組みに変える必要性が一気に高まった。
そこで動いたのが、大津赤十字病院の橋本氏である。長年の構想を現実の活動へと進めるべく、永田名誉教授をはじめ、芦原貴司・滋賀医科大学情報総合センター教授、西澤嘉四郎・近江八幡市立総合医療センター参事の3名に相談を持ちかけた。いずれも地域の医療情報基盤づくりをけん引してきたキーパーソンだ。
この三者の強い賛同を得て、「滋賀県の医療情報担当者を地域全体で育てていこう」という明確な合意が生まれ、活動は正式に動き出した。橋本氏が実務的なリーダーシップをとりつつ、「びわ湖あさがおネット」を支えてきた医師たちが後ろ盾となった。この協働体制が、今日の集いの方向性と底力を支えている。
既存組織を“土俵”にした立ち上げ戦略
この集いが短期間で定着し、成果を上げている背景には、発足時の戦略的な工夫がある。
特筆すべきは、スタート時に「びわ湖あさがおネット」という既存の団体を土俵として活用した点だ。集いの1回目から3回目までは、びわ湖あさがおネット事務局が公文書を出して参加者を募った。それが、「1病院がやりたいから」という呼びかけではなく、地域全体で公的に取り組む姿勢を示すことができ、多くの病院が参加しやすい環境を整えた。
現在、事務局機能は大津赤十字病院が担当し、運営も定着しているが、この初動の工夫が、他地域で同様の取り組みを始める際の重要なヒントとなる。医師会や病院協会、地域医療連携組織を「音頭取り」として活用する手法は、ゼロから団体を立ち上げるよりもはるかに参加のハードルを下げる有効な戦略といえる。
敷居の低さが生み出す現場の当事者意識
また、この集いが他の地域団体と一線を画すのは、「敷居の低さ」を徹底している点だ。
医療情報技師会など、資格や専門性に特化した集まりは全国に存在するが、この集いでは「資格は一切問わない」という。実際に、「日常業務ではシステムには片手間でしか関わっておらず、主な仕事は総務や医事」という担当者も積極的に参加している。
「分かっている人しか行けない」「スキルがないから無理」となりがちな専門集団のイメージを払拭し、システムに関わる全ての人が「主人公になれる場」を目指している点は注目される。
運営面でも工夫がある。会議は週末や夜間ではなく、平日業務時間内に開催する。そのため、病院側は活動を「自己研さん」ではなく「業務」として認め、参加者は院内の理解を得て出席できる。これは、病院の経営層に対し、この活動が病院運営にとって不可欠な業務であることを示すメッセージにもなっている。
第5回会議で見えた「共助」のリアリティー
2025年11月6日に開催された第5回の集いでは、IT-BCPの現状と地域連携のあり方、システム更新のコスト問題、具体的な業務システム導入事例などのテーマで活発な意見交換が繰り広げられた。

サイバー攻撃時、病院はどう助け合うか
最も熱を帯びたのは、サイバー攻撃が自院で発生した時に、近隣病院と、どう連携するかだった。
議論の焦点は、サイバー攻撃を受けてしまったことを「恥ずかしい」と感じても、近隣に報告や助けを求める声を上げられるかという切実な懸念に集まった。インシデントはニュースになり、病院の評判を落としかねないという経営側の視点が、その背景にある。
芦原貴司・滋賀医科大学情報総合センター教授は、「『明日はわが身』であり、隠さずオープンにすることが必要だ」と説き、「中の人は混乱しているため、冷静に第三者的な観点から意見を言える人を周りに置く体制が必要だ」と指摘した。
また、河南智晴・大津赤十字病院副院長は、徳島県のつるぎ町立半田病院がランサムウェア攻撃を受けた事例を引き合いに出し、緊急時の「横のつながり」の重要性を語った。攻撃により院内端末をすべて使用不能にせざるを得なくなった際、近隣の病院が「余っている端末を使ってください」と機器を融通し合い、最低限の診療を再開したという。
この出来事は、平時からシステム担当者同士のネットワークを築いておくことが、患者の安全を守る“最後のとりで”になると示している。河南副院長は、「被害に遭った病院が恥ずかしがらずに『助けてほしい』と言える関係を地域で育てることが大事だ」と強調した。
最終的には、「いざという時に吐露できないのでは、この会の意味がない」という認識に収れんし、「『犯罪による攻撃を受けたのであり、私たちは被害者なのだから助けてほしい』と声が出せる滋賀県にしていこう」という「お互いさま」の精神を再確認する場となった。
迫られる二要素認証対応、現場の実情
保健所からの立ち入り検査に関する報告をきっかけに、サーバーやネットワーク機器への二要素認証(MFA)対応が議題に上った。国は2027年度中の実運用を求めており、未対応の場合には改善命令の対象となる可能性があることから、対応の必要性が参加者間で改めて共有された。
一方で、現場の実態は制度の要請に追いついていない。多くの病院では電子カルテ更新時に対応を予定していたものの、サーバーやネットワーク機器まで適用するための費用面や技術的ノウハウの整理が十分に進んでおらず、参加施設の中で実際に対応できている病院はなかった。
参加者からは、「補助金がないなら費用を病院から出すことになるが、その費用はいくらなのかさえ誰も知らない」という切実な声が上がった。これに対し、「国や県が補助を検討できるように、むしろ現場から『これだけ費用がかかる』という具体的な数字を示すべきだ」との提言がなされ、抽象論にとどめず政策提言につなげようという意見も出た。
失敗事例から学ぶシステム導入の教訓
AI(人工知能)問診システムやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)導入に対する生々しい「失敗」の共有も行われた。
ある中核病院では、AI問診システムを安価で導入したが「別人の情報が表示される」「データが消失する」などの度重なるトラブルが発生し、2カ月間のシステム停止に至ったという。担当者は、システム構成が、大規模病院の安定稼働に必要な堅牢性を備えていなかった可能性や、診療科ごとにカスタマイズしすぎたことがトラブルの背景にあった可能性を挙げた。
そして、この報告から、「AI問診はAIというより電子化と割り切り、期待しすぎない方がよい」「カスタマイズよりも標準仕様での運用を優先する」「導入は一気に広げず、スモールスタートで安定性を確認すべき」といった、他病院にとって即座に役立つ具体的な教訓が共有された。
一方で、看護師の配置削減(人件費効果)が実感されており、現場、特に医師や看護師からは「ないよりはあった方が楽」としてシステム利用が強く要望されている現状も明らかになった。
別の病院からは、ホームページの問い合わせフォームへのサイバー攻撃が報告された。日曜日に当直者1人という状況で大量の不審メールが届き、パニック状態となるなか、直ちにメーリングリストに助けを求め、他病院のアドバイスと滋賀県警サイバーセキュリティ課の協力を得て、CGIのアップデートやIP制限などの対策を講じて事態を収束させた。この事例は、「まさか」が起こった時に孤立せず、泣きつく先となるネットワークが精神的・実務的な支えとなったことを象徴している。
他地域でも応用可能な「滋賀県モデル」成功の条件
「滋賀県病院医療情報システム担当者の集い」が短期間で機能している理由は、技術や予算の多寡ではなく、活動を継続させるための運営上の工夫にある。他地域で同様の「横のつながり」を構築する上で、4つのポイントがある。
一つ目は、主導権を持って活動を継続させるキーパーソン(担当者)の存在。そして、初動では、地域で認められている既存の組織(病院協会や医師会、地域医療連携ネットワークなど)の枠組みを利用し、公的な活動としての信頼性を確保することだ。
二つ目は、活動を「自己研さん」ではなく「病院業務」として位置づけるために、平日昼間に開催すること。これは、経営層に活動の重要性を理解させる強力なメッセージとなる。
三つ目は、参加の敷居を下げ、システムに関わるすべての職員を対象とし、専門的な知識がなくても課題を共有し、助けを求められる「顔の見える関係」を優先することも欠かせない。
最後は、会議で議論するだけでなく、メーリングリストなどの安価なツールを活用し、日常的な情報共有と緊急時の「泣きつく先」としての機能を維持することだ。「こんなことで困っています」と投げれば、誰かが反応してくれる体制が、担当者の大きな安心感になる。
「滋賀県病院医療情報システム担当者の集い」は、医療情報担当者が立ち上げ、地域全体で患者を守るという最終目標を掲げ取り組んでいる。この「滋賀県モデル」が、全国に広がれば、医療のIT基盤はより強固なものとなっていくだろう。