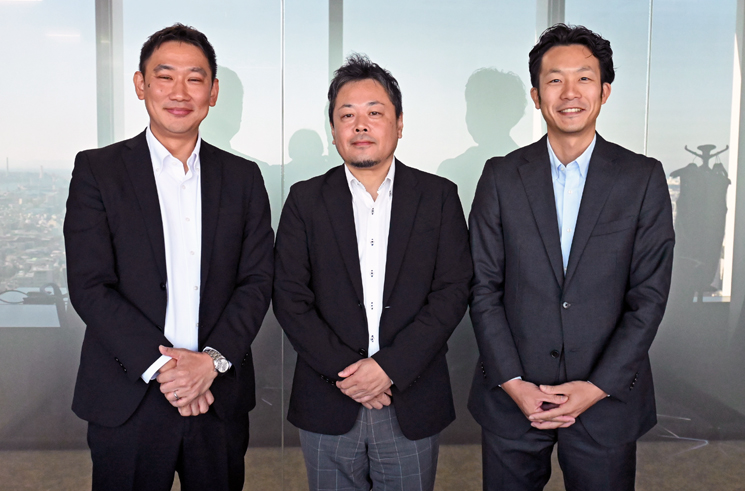医療現場で進むAI活用の現在地と課題 荻島創一・東北大教授に聞く
掲載日:

荻島創一・東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 ゲノム医科学情報学分野教授
医療でAI(人工知能)の導入が進んでいる。ビジネスでのAIを活用した業務効率化の取り組みが広がる中、医療分野でも画像診断支援などを始めとするさまざまなAIサービスが登場している。医療のAI活用はどこまで進んでいるのか。日本メディカルAI学会の評議員を務め、医療AIの動向に詳しい、荻島創一・東北大学東北メディカル・メガバンク機構ゲノム医科学情報学分野教授に聞いた。(取材:医療テックニュース編集部)
生成AIの医療AIは3種類
――医療AIで特に注目している分野はありますか。 …