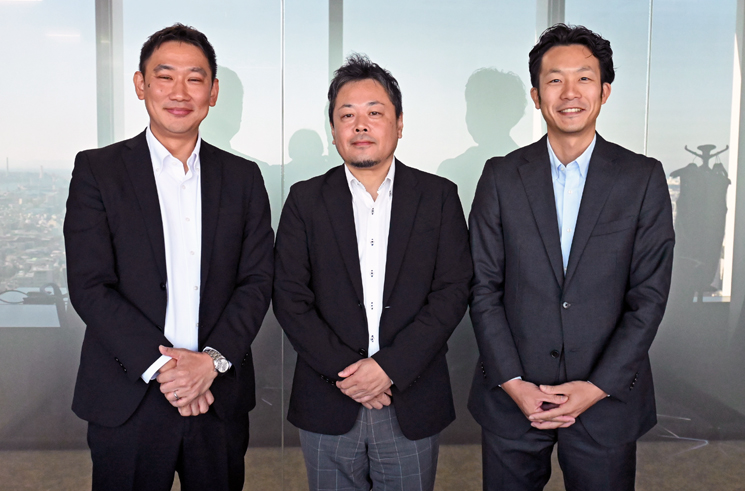【DTx対談】治療用アプリで食事療法に変革を起こす
京都大学とaskenの特定臨床研究を通じた共同開発
掲載日:
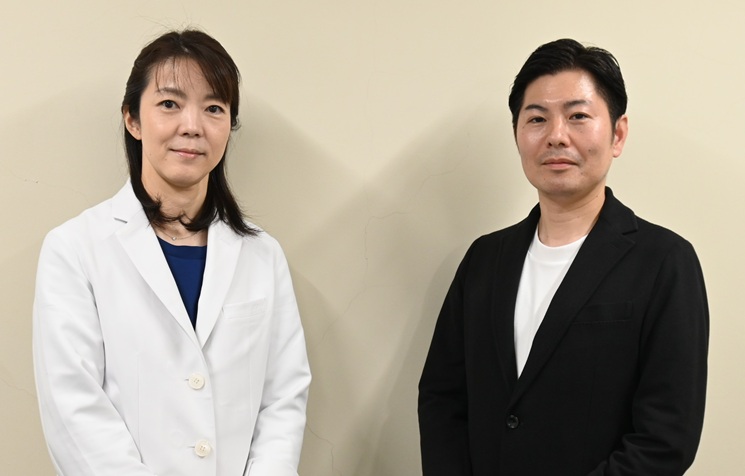
(左から)京都大学医学部付属病院 先端医療研究開発機構 池田香織氏と、松尾恵太郎氏・asken医療事業部部長・法人事業部長
医療におけるデジタルトランスフォーメーション「医療DX」が推進され、全国の医療機関では電子カルテをはじめ診療の業務フローにさまざまなデジタルサービスが組み込まれている。このデジタル化の流れの中で、注目が集まる「デジタル治療(DTx:デジタルセラピューティクス)」を聞いたことはあるだろうか。DTxは、疾患の予防や管理、または治療を目的としたデジタル製品で、プログラム医療機器(SaMD:医療機器としての目的性を有するソフトウェア)のひとつとされている。国内でも新たな治療の選択肢としてDTxへの期待が高まっており、デジタル治療に関するサービス開発や治験が進んでいる。
今回は、治療用アプリの食事療法への活用をテーマに取り組む、京都大学の池田先生とAI(人工知能)食事管理アプリ『あすけん』を提供するaskenの松尾氏に話をうかがった。医療現場における治療用アプリの活用について、特定臨床研究を経て医療現場に適する治療用アプリの開発の裏側にせまった。(取材:医療テックニュース編集部 采本麻衣)
治療用アプリで、“楽しみながら食事を良い方向に変えていく”食事療法の実現に取り組む
――ヘルスケアアプリ事業者であるaskenと池田先生の出会いは? …