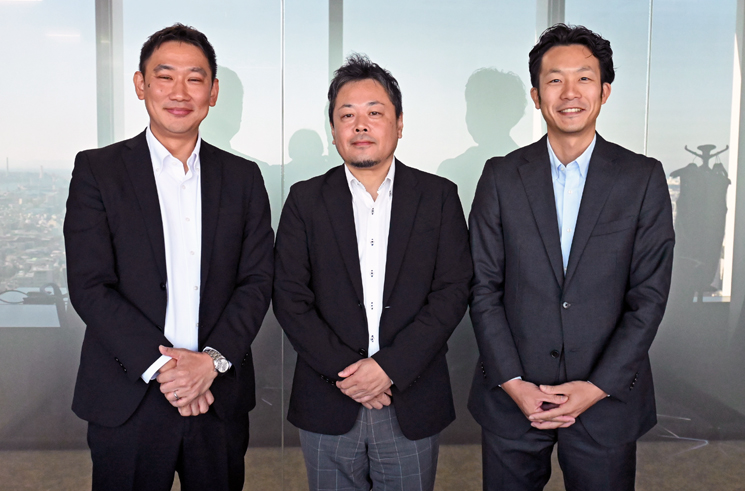スマホにチャットなど、汎用ITツールやシステムの活用で病院DXを実現
HITO病院のデジタル戦略
掲載日:

HITO病院(愛媛・四国中央市)
HITO病院は、愛媛県四国中央市にある病床数228床の地域中核病院だ。2024年の1月に、戦略的ダウンサイジングで、急性期病棟を3つから2つに減らし稼働率を上げ、ほぼ満床に近い形で病棟運営を行っている。さらに、DPC(包括医療費支払制度)で平均在院日数を短縮しながらも、診療報酬単価を向上。人材確保が難しくなる中で、病床規模を縮小し、地域に求められる医療の持続可能性を追求し、「病院DX(デジタルトランスフォーメーション)」を推進、働きやすい職場環境への見学希望が全国から後を絶たない。
「病院DX」の成功のカギは何か。取り組むうえでの課題も含め、HITO病院 脳卒中センター脳神経外科部長 兼DX推進室CXO(チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー)の篠原直樹氏、DX推進CIO(チーフ・インフォメーション・オフィサー)の佐伯潤氏に聞いた。(医療テックニュース編集部 副編集長 米谷知子)
HITO病院の医療DX推進体制
――貴院ではどのような体制で医療DXを推進していますか?
佐伯氏:地域のみなさまが住み慣れた町で、健康に暮らしていくために、「いきるを支える」未来を創り出すために、2017年から「未来創出HITOプロジェクト」を実施しています。「HITO」の視点を踏まえてICT(情報通信技術)の利活用を推進し、医療と介護の質と業務効率の向上に努めてきました。プロジェクトの推進メンバーは、理事長をトップとして、病院長、副院長、DX推進室、各部署の管理者で構成されています。
篠原氏:「DX推進室」は理事長直轄の部署です。私はCXOとして企画を担当し、佐伯はCIOとして、病院の情報管理や企業の調整などを行っています。現場との調整や、企業と一緒にシステム開発などを行う場合は、DX推進室HIA(ホスピタル・インフラストラクチャー・アーキテクト)の村山が対応しています。主力メンバーは理事長を含めた4人で、チャットを活用して検討や承認を行っています。また、各部署の管理者は、案件に応じてDX推進室のメンバーと一緒に業務を進めています。
――DXを推進する上で、体制上の工夫や課題はありますか?
篠原氏:苦労している点は課題抽出です。現場からの情報が上がってこないので苦労しています。そこで、バックキャスト思考を活用し、現在の課題や可能性を洗い出し、未来のビジョンを実現するためのアクションを計画しています。
また、現場の医師が多すぎると意見が分散しやすく、効率的な意思決定が難しくなるため、最初は小規模から始めています。加えて、案件を開始する際は、各部署に出向いて対面で話をするようにしています。現場に対して、強制ではなく、必要であれば使ってもらうという姿勢で臨んでいます。
――脳神経外科の篠原先生が、医療DXの推進に関わるようになったきっかけは何ですか?
篠原氏:以前、他院からの医師の引き上げで、脳神経外科の医師が私1人になったことがありました。それをきっかけに、救急を受けたり、地域の診療体制を維持したりするために、電話に替えてスマートフォンと業務用チームチャットを導入しました。これによって、ストレスが軽減されました。
「医師の働き方改革」の流れの中で、「タスク・シフトとシェア」が求められていますが、組織の規模が大きくなればなるほど、ICTツールが必要です。チャットの活用で、私自身、業務負担が軽減されることを実感したため、他の部署にも広げていきたいと思い、院内の医療DXに取り組むようになりました。
「コミュニケーション」変革で時間を創出し、AI活用で「記録業務」省力化を目指す
――具体的にはどのような取り組みを行っていますか?
篠原氏:われわれは、「医療DX」ではなく、「病院DX」という言葉を使っています。デジタル技術を使って、自院のトランスフォーメーションを行うという意味合いです。医療全体をデジタルの力で変えることは、われわれにはできません。政府が推進している「医療DX」は、もう少し地域でも進んできた段階で、遅れないようについていきたいと思っています。
当院が「病院DX」に取り組む理由は、各職種が本来の業務に集中できる環境を作るためです。本来業務に集中する時間を創出するために、手段としてICT活用による効率化があると考えています。例えば、チャットを活用することで「報連相」を効率化し、時間を創出できます。本来業務がきちんとできないと、「働きがいのある職場」にも、「働きやすい職場」にもなりません。また、今後地域で医療職を確保することも難しくなってきます。
篠原氏:当初は「音声入力」を導入しようと考えていましたが、時間を創出する一番の手段は、「チャット」です。集まってミーティングをする必要も、人を探す必要もなくなる。待つ時間もなく、電話で時間を奪われることもない。ほかのテクノロジーを入れたとしても、チャットほどの効果を得ることは難しいと思っています。
まずは「コミュニケーション」の変革で時間を創出する。その次は「記録業務」。病院は記録業務が多いので、生成AI(人工知能)を活用して記録の省力化を図ることが次のステップです。これは、まだ始めたばかりで、あまり進められていません。なぜなら、「チャット」は既に社会に浸透しており、多くの人が使い方を熟知していますが、生成AIの活用はこれからなので、もう少し時間がかかるのではないかと思います。
篠原氏:電子カルテは紙に書いていたものを電子化しただけで、「電子カルテの情報を活用する」というコンセプトでは作られていません。「記録業務」にAIを活用する方法は、AI搭載のスマートフォンやPCを使用して、情報を抽出し、わかりやすく整理することです。例えば、医師や看護師は、「入院診療計画書」や「退院時サマリー」を作成しますが、このような書類作成業務でAIを活用することを想定しています。
もう1つは「音声入力」です。現状は、滑舌が悪いと正しく表記されず、手直しが必要になりますが、生成AIを活用すれば、話した内容がそのままテキスト化され、そのテキストをもとにきちんとした文章を生成できます。
佐伯氏:現状では、多くの生成AIはクラウド上で動作します。この「クラウドAI」と「医療情報システム」を接続することは、技術面・セキュリティ面のハードルが高く、難しい課題です。そういう意味では、AIがクライアント端末で動作するようになれば、セキュリティを担保しながらリアルタイムの応答が可能になり、ユーザーレベルでもAIの活用が進むのではないでしょうか。
「病院DX」で柔軟な働き方にシフト、脳神経外科・脳神経内科医が週休3日で時間外労働減少
――これまでの「病院DX」の取り組みから、どのような成果や効果がありましたか?
篠原氏:「病院DX」の成果や効果はさまざまです。まず、多職種間でコラボレーションが進んだため、助け合える環境が整い、人間関係の質が向上しました。また、柔軟な労働環境が整備されており、一部の職員はリモートワークを活用しています。SCU(Stroke Care Unit:脳卒中専門の集中治療室)で働く脳神経内科医や脳神経外科医は、週1回の当直はあるものの、週休3日制が可能になりました。週休3日でも、モバイル端末で情報が得られるので、病院の状況はわかります。フレキシブルな働き方ができるようになったことで、時間外労働も減りました。
さらに「多職種協働セルケアシステム」の導入で、看護師はナースステーションに戻ることがほとんどなくなり、ベッドサイドの滞在時間が増え、患者との距離が縮まりました。「多職種協働セルケアシステム?とは、看護師やメディカルスタッフが「セル」を構成し、ベッドサイドを中心にチームとなって、それぞれの職種が専門性を生かしながら連携して患者を担当する仕組です。新人看護師が辞めることもなくなり、コロナ禍でも、救急患者をたくさん受け入れられました。
経営的な視点では、2024年の1月に、戦略的ダウンサイジングを実行しました。急性期病棟を3つから2つに減らして稼働率を上げ、ほぼ満床に近い形で病棟運営を行っています。また、DPC(Diagnosis Procedure Combination:包括医療費支払制度)で平均在院日数を短縮しながらも、診療報酬単価は上がっています。人材確保が難しくなる中で、病床規模を縮小し、あえて忙しい状況を作りながらも、スタッフの負担にならないような働き方を模索しています。
課題は、最近、企業でもいわれている「人的資本経営」の推進ではないかと思っています。人を育成し、キャリア形成できる環境を作らないと、当院を選んでもらえません。看護師に投資したように、今後、病院として「こういう分野に力を入れていきたい」というところに、人材育成投資をしていきたいと考えています。
――スマートフォンや業務用チャットツールの導入で、院内コミュニケーションはどのように変わりましたか?
篠原氏:スタッフ間のコミュニケーションは、スマートフォンのチャットアプリで行うことがほとんどです。臨床現場で患者情報を共有する場合は、電子カルテの引用機能を使うと便利なので、電子カルテ内のチャット機能を利用しています。事務的なものは、マイクロソフトの「Teams(チームズ)」を使っています。これまでは、メールを見るなど、自分で情報を取りにいかなければなりませんでしたが、今は、さまざまな情報が手元にプッシュ通知で届くので、迅速に対応できるようになりました。
PHSも持っていますが、看護師など一部の職種以外は、あまり使っていません。看護師は、「ナースコールシステム」と「PHS」が連動しているのでPHSを使っていますが、「多職種協働セルケアシステム」を導入し、ナースコールが必要ない環境を整備しました。このように、「スマートフォン」に「ナースコールシステム」をつながずに済むよう、新しい見守りシステムの導入に加えて組織の働き方自体を見直しました。
「多職種協働セルケアシステム」にした理由は、認知症患者やリハビリ患者が増えたことで、ベッドサイドで患者に寄り添い、必要なケアを提供することが重視されるようになったからです。また、高齢患者の増加により、ナースコールを使えない人も増えてきています。「スマートフォン」と「ナースコールシステム」の接続に1000万円以上かかるという費用の問題もありました。
誤解がないように言っておくと、チャットの使用を強制したわけではなく、選択肢として提供しただけです。チャットの方が、おのおののタイミングでストレスなく発言できるということで、結果的にチャットでのコミュニケーションが増えました。もちろん、急ぐ場合やチャットで返信がない場合は電話がかかってくることもありますし、対面で会議をすることもあります。
ビジネスで利用されているツールを医療現場にアレンジし活用
――どのようなシステムやサービスで対策を行っていますか?
篠原氏:基本的には、あまり教育しなくても使えるようなコモディティ化したシステムやサービスを導入するようにしています。また、IT人材を確保しようと思うとコストもかかりますし、なかなかヘルスケア分野には来てもらえません。そこで2024年度に、「令和4年度 愛媛県アジア高度IT人材受入促進事業」 を活用し、ネパールの優秀なIT人材1名を、DX推進課に迎え入れました。現在、彼がさまざまなアプリを作ってくれています。
佐伯氏:当院でもICT人材はなかなか見つかりません。そのため、「一般的なPCの知識があればできる業務」と「専門的な業務」を分けて、専門的な業務は高度IT人材が対応しています。また、オンライン形式で、外部の力を借りることもあります。
篠原氏:おカネと時間をかけて独自開発したとしても、受け入れられるかどうかはわからない。医療分野以外で、一般に受け入れられている便利なものがあれば、安く早く取り入れられる。まずはそこから始めた方が失敗は少なくなると思っています。
――ビジネスで使われている汎用(はんよう)的なシステムやサービスでも使えるのですか?
篠原氏:例えば、「チャット」などは導入が簡単です。大事なのは、それをどのように使って、どのように組織を変革するかです。いろいろなテクノロジーを入れると、入れただけで終わってしまうリスクがあります。ほかの分野で社会実装されているものを、いかに医療現場にアレンジして成果を出していくか。プライベートでは「LINE」などでコミュニケーションを取ることが一般的ですが、病院でもチャットツールは使えます。
テクノロジーの導入で、「今までできなかったことができるようになる」ということは、「今までの働き方を変える」ということなので、本当の意味での「働き方改革」になるよう調整が必要です。単に労働時間を減らすのではなく、生産性を落とさないよう、よりよい働き方にしていくためには、ここ数年は、みんなが使い慣れているものを工夫して使っていく方がよいと思っています。
当院の場合は、「パーパス(社会的存在意義)」として、「いきるを支える」ということを掲げています。それに関係することであれば、ルールを変えても否定されることは少ない。あるテクノロジーを導入する際は、「パーパスに見合う働き方」に変えられるようなルールを作る。その作業自体が、病院におけるDXだと思っています。
病院における「働き方」をどのように変えればよいのかは答えがありません。したがって、まずは使い慣れた汎用的なもので対応していく。最近よく言うのは「OODAループ(Observe:観察、Orient:状況判断、Decide:意思決定、Act:実行の4つのフェーズを繰り返して運用することで、素早い意思決定や行動を促すフレームワーク)」の考え方です。
みんなで共有し、意思決定に持っていく。仮説を立てる際も、モバイルのセキュアインターネットで調べたり、生成AIに聞いたり、グループチャットのメンバーに聞いたりできるようになりました。意思決定の結果も、行動の結果も、すぐにチームチャットで共有できる。こういったことができるようになったので、楽に働けるようになり、ストレスが減ってきたように思います。
「DX」は「D(デジタル)」の方が、クローズアップされがちですが、どのように「トランスフォーム」するかが重要です。「トランスフォームをしたい。であれば、このデジタル技術が使えるか」という考え方で進めなくてはいけない。一方で、デジタル技術を使わない組織変革も必要と考えています。
病院間で、好事例を共有することは難しいと感じています。そのため、企業におけるコラボレーションツールの好事例やAI活用事例を医療現場に共有し、病院に転用することを考える必要があると思っています。すでに企業で広がっている新しい技術やアプローチで、医療現場では、まだ普及していないものがたくさんあります。そういったものを取り入れることで、企業の市場が広がるとともに、医療現場には変革がもたらされると思います。
佐伯氏:一般的に、医療現場はセキュリティを重視してオンプレミス環境を選択するイメージがあるかもしれません。しかし、クラウドを活用することで、これまでの運用を改善できる可能性もあります。当院でもオンプレミス型のシステムを利用しているので、ハードルが高いところもありますが、割り切って考えることも大切だと思っています。
――「病院DX」に取り組んだ結果、人材確保にはよい影響がありましたか?
篠原氏:東京から、「IT活用が進んでいるので、HITO病院で働きたい」というキャリア2年目の若手看護師が来てくれたので、少しは効果があるように思います。また、3年前から新人看護師には「iPhone」とは別に、「iPad mini」を支給し、「eラーニングシステム」を導入しました。コロナ禍で、対面の研修があまり受けられない人たちを対象に実施したところ、一般的には離職率10%といわれているところ、3年連続で離職者ゼロになりました。
政府の医療DX施策への対応
――政府が進めている医療DXへの対応状況を教えてください。
佐伯氏:現状は、「マイナ保険証」に対応しています。「電子処方箋」は、システムの導入は完了していますが、本格稼働は2024年の秋ごろに開始予定です。医師資格証(HPKIカード)がなかなかそろわないので、そろい次第開始したいと考えています。「標準型電子カルテ」は、状況を見ながらキャッチアップしていきたいと考えています。
――そのほか、政府の取り組み対して、どのようなことに関心がありますか?
篠原氏:1つは病院として「リスキリング」にどのように関わっていくか。これまでの「リスキリング」は、学会などが専門職の能力を強化してきました。専門職は多くのスキルを持てるようになり、今後、コラボレーションによって、さらなる価値が生まれてくるのではないかと思っています。
医療や介護に携わる人たちに、どのような知識や経験があれば、よりよいサービス提供につながるか、学習内容を検討しています。マルチタスク人材を育てるには、いろいろな考え方を取り入れる必要があると思っています。政府のリスキリング支援も最大限に活用していきたいと考えています。
もう1つは、「GX(グリーントランスフォーメーション)」です。昨今、電気代が高騰しているので、電気代を抑えるとともにCO2の削減にもつなげていきたいと思っています。いいことばかりではありませんが、GXのよいところにフォーカスして取り組んでいく予定です。
人手不足は、「多職種間の連携強化」とAIなど活用した「個人の能力拡張」でカバー
――今後の取り組みを教えてください。
篠原氏:人材不足に直面する一方で、生成AIを活用すると、いろいろな情報が得られることがわかってきたので、AIを活用して個人の能力拡張につなげていきたいと思っています。スタッフのiPhoneにはマイクロソフトの「 Copilot(コパイロット)」も入っており、ウェブ検索や院内情報をもとに回答を生成することもできます。
人手不足は「連携の強化」と「個人の能力拡張」でカバーするしかない。院内で完結できないなら、地域の垣根を越えたコラボレーションツールが必要です。「コラボレーションツール」や「モバイル端末」があれば、人材不足でも、なんとか乗り切っていけるのではないかと考えています。
医療DXで最初の一歩は「コラボレーション強化」
――医療DXを推進するには、どのようなことに気を付ければよいでしょうか?
篠原氏:まずは、1人1台スマートフォンによるネットワーク構築を行い、グループチャットで情報共有を行い、対話を増やして「協働」を促進するところから始めるとよいと思います。大手企業もさまざまなコミュニケーションツールを導入して、時間や場所に縛られないような働き方を実現しています。
若い人にとっては、対面や電話でのコミュニケーションより、チャットのコミュニケーションの方が、ストレスが少ないようです。そうすることによっていろいろな意見を聞け、新しいことが生まれてくる可能性がある。そういった情報をもとに、AI活用等が進んでいくのではないかと思います。最初の一歩としては、「コラボレーションを強化する」ことが重要と考えます。